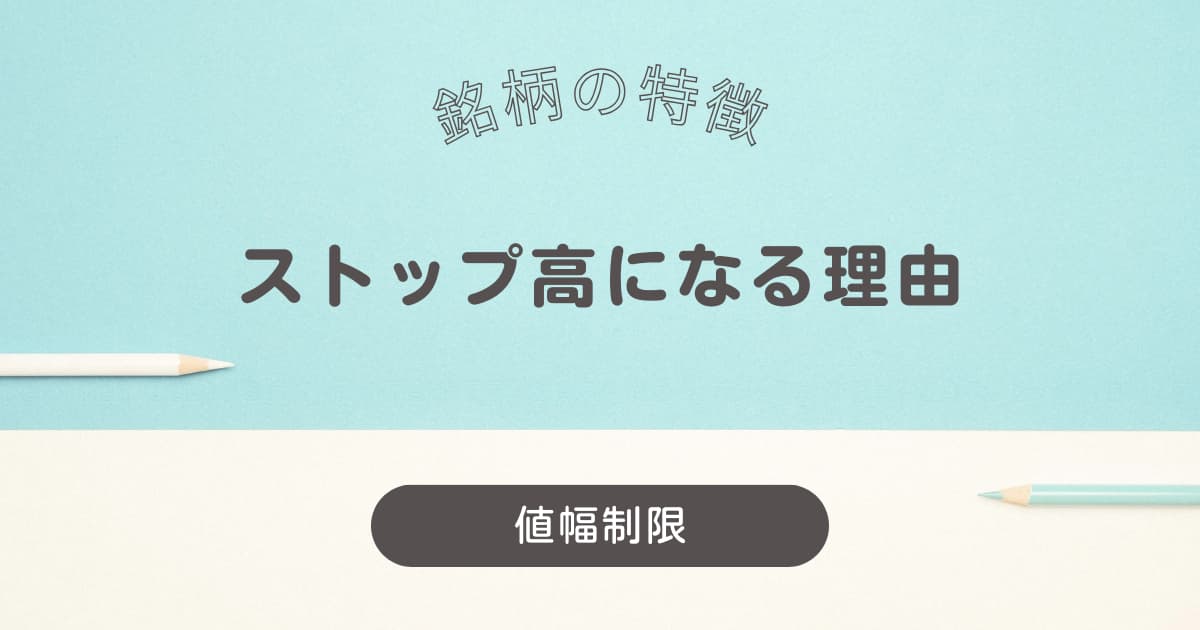「ストップ高」という言葉を聞いたことはあっても、その意味や理由まではよく分からないという方も多いかもしれません。
株価が急に上がって取引が止まるこの現象には、いくつかの特徴や共通点があります。
この記事では、なぜストップ高になるのか、その理由と銘柄の特徴を、株を始めたばかりの方にも分かりやすく説明いたします。
\ 株の分析に使っているチャートツールTradingView /
- 初心者でも直感的に使いやすいUI
- 高機能なテクニカル分析ツールが無料で利用可能
- PC・スマホ・タブレットでチャート分析が可能
- ソーシャル機能で他の投資家のアイデアを学べる
ストップ高とは?

日本の株式市場では、1日の間に株価が動く範囲に「上限と下限」が決められています。この決まりを「値幅制限」と呼びます。
たとえば、ある銘柄の株価が1,000円だった場合、値幅制限が10%であれば、その日は1,100円までしか上がらない仕組みです。
それ以上に株価が上がることは、その日には起きません。
このように、株価がその上限いっぱいまで上がってしまった状態を「ストップ高」といいます。

1. 値幅制限と更新値幅一覧
| 価格 | 値幅制限 | 更新値幅 |
| ~100円未満 | 30円 | 5円 |
| 100円以上~200円未満 | 50円 | 5円 |
| 200円以上~500円未満 | 80円 | 8円 |
| 500円以上~700円未満 | 100円 | 10円 |
| 700円以上~1,000円未満 | 150円 | 15円 |
| 1,000円以上~1,500円未満 | 300円 | 30円 |
| 1,500円以上~2,000円未満 | 400円 | 40円 |
| 2,000円以上~3,000円未満 | 500円 | 50円 |
| 3,000円以上~5,000円未満 | 700円 | 70円 |
| 5,000円以上~7,000円未満 | 1,000円 | 100円 |
| 7,000円以上~10,000円未満 | 1,500円 | 150円 |
| 10,000円以上~15,000円未満 | 3,000円 | 300円 |
| 15,000円以上~20,000円未満 | 4,000円 | 400円 |
例えば、株価1,500円の場合、ストップ高は 1,800円(1,500円 + 300円)となります。
2. 2つのパターンがある
ストップ高には、大きく分けて2つのケースがあります。
1つ目は、取引が始まってから株価がぐんぐん上がり、その途中でストップ高に達する場合です。
このときは、しっかりと取引が行われながら、株価が制限いっぱいに達します。
2つ目は、朝から「買いたい!」という注文がたくさん入りすぎて、売ってくれる人がいないまま、取引が始まらずにそのまま終わってしまうパターンです。
この場合、発表されたニュースや材料が「とても良い」と判断され、業績や成長に対して強い期待が集まっていることが多いです。
3. ストップ高を調べる方法
「今日はどの銘柄がストップ高になったのか?」ということは、証券会社の取引ツールや、ニュースサイトなどで毎日確認することができます。

以前にどんな銘柄がストップ高になったのかを調べたい場合、「株探(かぶたん)」という株情報サイトを使うと便利です。
無料版では、約1か月前までのストップ高銘柄を見ることができます。
それより前のデータを見たいときには、「株探プレミアム」という有料のサービスを利用する必要があります。
このプレミアムサービスを使えば、2013年9月以降のストップ高をすべて調べることが可能です。
ストップ高になる6つの理由

株価がストップ高になると、「何が起きたの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
ストップ高には、いくつかのはっきりとした理由があります。
ここでは、主に見られる6つのきっかけについて、順番にご説明いたします。
1. 良い決算が発表されたとき
会社が出す決算が、予想よりも良かったときには、株価が急に上がることがあります。
とくに「売上がたくさん伸びている」「今後も成長が続きそう」と判断された場合には、多くの人が株を買いたがり、ストップ高になることもあります。
当ブログで紹介している銘柄の中には、決算の翌日にストップ高になるものがよく見られます。
また、決算発表が集中する時期は、ストップ高になっている銘柄の多くが、決算を出したばかりの企業ということも多いです。
2. 会社の成長や新しい事業の発表
企業が「これからもっと儲かります」と発表したり、「新しいことに挑戦します」と知らせたりすると、その期待で株価が上がることがあります。
たとえば、海外への進出や新しいサービスの開始など、将来に向けた前向きな発表があったときには、投資家の期待が高まり、ストップ高になることも少なくありません。
3. 業界全体が好調なとき
特定の業界に追い風が吹いている場合、その流れに乗って関連の株価も上がることがあります。
たとえば、「半導体がたくさん使われるようになった」というニュースが出ると、半導体を作る会社の株がまとめて上がることがあり、その中の一部がストップ高になることもあるのです。
4. 買収や合併のニュースが出たとき
会社どうしがくっついたり(合併)、一方がもう一方を買い取ったり(買収)するニュースも、株価を大きく動かす原因になります。
たとえば、大手企業に買われた会社は「これからもっと成長しそう」と思われることがあり、株価が跳ね上がってストップ高になることもあります。
また、買う側の企業にも「お互いに力を合わせればもっと儲かるかも」といった期待が出て、株価が上がることがあります。
5. 新しい製品やすごい技術が発表されたとき
だれもが驚くような新商品や、便利な新技術を発表すると、将来の儲けが期待されて株価が上がることがあります。
たとえば、「今までにない省エネの電池」や「新しい治療法」などが発表されれば、その会社に注目が集まり、ストップ高になるケースも出てきます。
6. 思惑での売買の影響
短い期間での儲けを狙って、ある銘柄に資金を集中させる人たち(仕手筋)が動いたときにも、ストップ高になることがあります。
このような動きは、特に理由がなくても値段だけが上がる場合が多く、あとで急に値下がりすることもあります。
ですから、このようなケースでは、長く持ちたい人にとって注意が必要です。
ストップ高のリスク

株価がストップ高になると、なんだかとても良いことのように思えますよね。たしかに株価が大きく上がっている状態ではありますが、その裏には注意すべきポイントもあります。
ここでは、ストップ高にまつわる3つの主なリスクについてお伝えします。
1. 売りたい人が増える可能性がある
株価が急に上がると、「今のうちに売って利益を出そう」と考える人が増えます。その結果、次の日にたくさんの売り注文が出て、株価が大きく下がることもあるのです。
とくに、短い期間で値上がりした銘柄は、下がるスピードも速くなる傾向がありますので、注意が必要です。
2. 市場が反応しすぎていることがある
ストップ高の原因が「ちょっと良いニュース」だけという場合もあります。
そういった一時的な材料で株価が上がってしまうと、あとから「やっぱり上がりすぎだった」と気づかれ、値段が元に戻ることもあります。
このように、期待だけが先に広がりすぎると、あとで反動がくることがあるのです。
3. 高いところで買ってしまう危険がある
ストップ高になると、「もっと上がるかも!」とあせって買いたくなるかもしれません。しかし、そのときはすでに多くの人が株を買っていて、値段が高くなりすぎていることもあります。
このタイミングで買うと、その後に株価が下がったとき、大きな損をする可能性があるのです。これを「高値づかみ」といいます。
急騰銘柄に飛びつく前に、個人投資家が負けやすい理由も知っておくべきです。
まとめ
ストップ高には、良い決算や新しい事業の発表、買収など、いくつかの共通した理由があります。しかし、株価が急に上がったからといって、必ずしも安心して買えるとは限りません。
表面のニュースだけで判断せず、企業の中身や将来性をしっかりと調べることが大切です。
冷静な目で銘柄を選ぶことで、失敗の少ない投資につながりますので、ぜひ今回の内容を今後の参考にしていただければ幸いです。
銘柄選びの基礎として、株式投資の重要用語も押さえておきましょう。