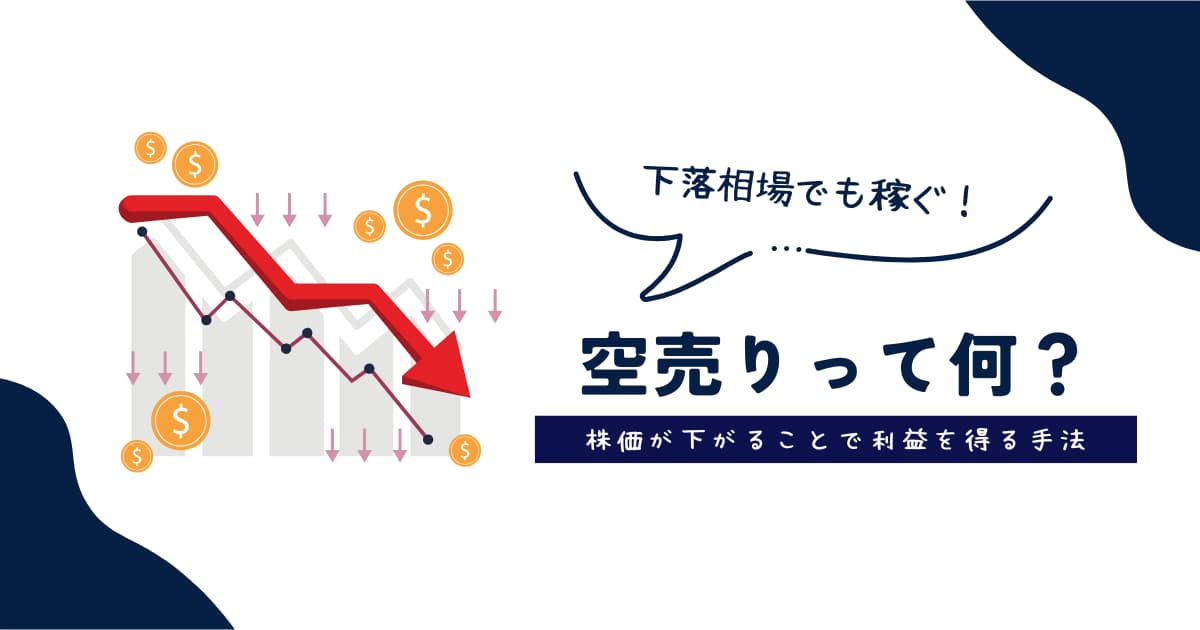株の売り買いには「安く買って高く売る」以外にも、もうひとつの考え方があります。それが「空売り」という方法です。
これから株価が下がりそうな株を先に売り、あとで買い戻すことで利益を狙います。ただし、空売りには注意しなければならない点も多くあります。
この記事では、始める前に知っておきたい基本と、損をしないための工夫について解説します。
\ 株の分析に使っているチャートツールTradingView /
- 初心者でも直感的に使いやすいUI
- 高機能なテクニカル分析ツールが無料で利用可能
- PC・スマホ・タブレットでチャート分析が可能
- ソーシャル機能で他の投資家のアイデアを学べる
空売りとは?

空売りとは、株の値段が下がることで利益を出すための方法のひとつです。
普通は、「安いときに株を買って、高くなったら売る」というのが基本のやり方です。
ですが、空売りはその反対で、「今ある株を借りて売り、あとで安くなったところで買い戻す」という流れになります。
たとえば、Aさんが100円の株を持っていたとします。
あなたはそれを一時的に借りて、100円で売ります。そして、あとでその株が80円に下がったときに買い戻せば、差の20円があなたの儲けになります。
このように、空売りは「これから株が下がりそうだ」と思ったときに使うことが多いです。ただし、予想が外れて株価が上がってしまうと、大きな損をすることもあるため、注意が必要です。
具体的には以下のようなステップで行います。
- 株を借りる:まず、証券会社から株式を借ります。
- 売却する:借りた株式を市場で売却します。
- 株価が下落するのを待つ:株価が下がるのを待ちます。
- 買い戻す:株価が下がったタイミングで、売却した株式を買い戻します。
- 返却する:借りた株式を証券会社に返却します。
これらの取引により、売却価格と買い戻し価格の差額が利益となります。

SBI証券の注文例
証券会社から借りるといっても特別なことはする必要はありません。
新規注文するときに、「信用新規売」を選び、注文をするだけです。ただし、すべての銘柄で注文できるわけではありません。
空売りは、決算発表や市場全体の流れによって大きく値動きすることが多い取引手法です。特に
四半期決算(1Q・2Q・3Q・4Q)の時期と株価の関係や、良決算でも株価が下がる理由を理解しておくことは、空売りの失敗を防ぐうえで欠かせません。
空売りのリスクと注意点

空売りは、株価が下がったときに利益を得ることを狙う方法ですが、うまくいくかどうかはリスクの管理にかかっています。
始める前に、どのような危険があるのかをしっかり理解しておきましょう。
1. 株価が上がってしまうリスクがある
空売りは「これから株の値段が下がるだろう」と思って行います。しかし、思いどおりに下がらず、反対に上がってしまうと、大きな損をすることになります。
たとえば、1000円の株を100株(合計10万円分)空売りしたあと、その株が1万円まで上がってしまったらどうなるでしょうか。
買い戻すときには、100株 × 1万円で100万円が必要になり、差し引き90万円もの損失が出てしまいます。
一方で、普通に株を「買って持つ」場合は、最悪でもその株が0円になってしまうだけです。
つまり、投資した10万円がゼロになるだけで、それ以上の損はありません。

2. 株を借りるための費用がかかる
空売りをするには、証券会社から株を借りる必要があります。そのため、貸株料(かしかぶりょう)という利息のようなお金がかかります。
さらに、「逆日歩」という追加の費用が発生することもあります。
これは空売りをする人が多すぎるときにかかる費用で、人気のある銘柄や在庫が少ない銘柄では特に高くなることがあります。

3. 少ないお金で大きな取引ができる分、損も膨らみやすい
空売りは、信用取引というしくみを使って行われます。これは、手元にあるお金よりも大きな金額の取引ができるという特徴があります。
このしくみを使うと、少ない資金でも大きな利益をねらえる反面、損失も大きくなりやすいという注意点があります。

4. 国のルールで取引が止められることがある
株の市場が大きく下がると、国の機関が空売りに関するルール(規制)を出すことがあります。これは、株価の急な下落を止めるためです。
このような規制が出されると、新しく空売りをすることができなくなったり、すでに空売りをしていた銘柄が急に制限されることがあります。

空売りでは、企業の財務状況や収益力を無視してしまうと、大きな損失につながることがあります。
特にPER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)などの指標を確認することが重要です。
空売りを活用する方法

リスクがある空売りですが、うまく活用することで利益を守ったり、チャンスを広げたりすることができます。
1. 株が下がりそうなときに利益を狙う
たとえば、業績が悪化している会社や、世の中で話題になりすぎて高くなりすぎている株などは、これから値段が下がる可能性があります。
そんなときに空売りを行い、株価が下がったあとで買い戻すことで、差額が利益になります。
2. 自分の持っている株の値下がり対策に使う
たとえば、将来性のある会社の株をたくさん持っていても、相場全体が悪くなると、いっしょに値下がりしてしまうことがあります。
そんなとき、別の銘柄を空売りしておくと、持っている株の損を、空売りの利益でカバーすることができます。これを「リスクの分散」といいます。
3. 一時的に高くなりすぎた株を狙う
ニュースや話題などで株価が急に上がったときは、あとから売る人が増えて株価が下がることもあります。
こういったタイミングで空売りを行えば、短い期間で利益を得られることがあります。ただし、値動きが激しくなりやすいため、すばやい判断が求められます。
4. イベントがきっかけで動く株をねらう
会社の決算発表や、新しい法律の発表など、大きなできごとがあるときは、その情報によって株価が動くことがよくあります
例えば、
- 決算が悪くなりそうなとき
- 裁判や行政の問題がありそうな企業
- 新しい事業が失敗しそうな場合
こうした「悪い情報が分かっているとき」に空売りを行うと、利益を狙えることがあります。
決算発表をきっかけに株価が大きく動くケースも多いため、決算短信の見方を事前に把握しておくことで、空売りの精度を高めることができます。
空売りの具体的な例
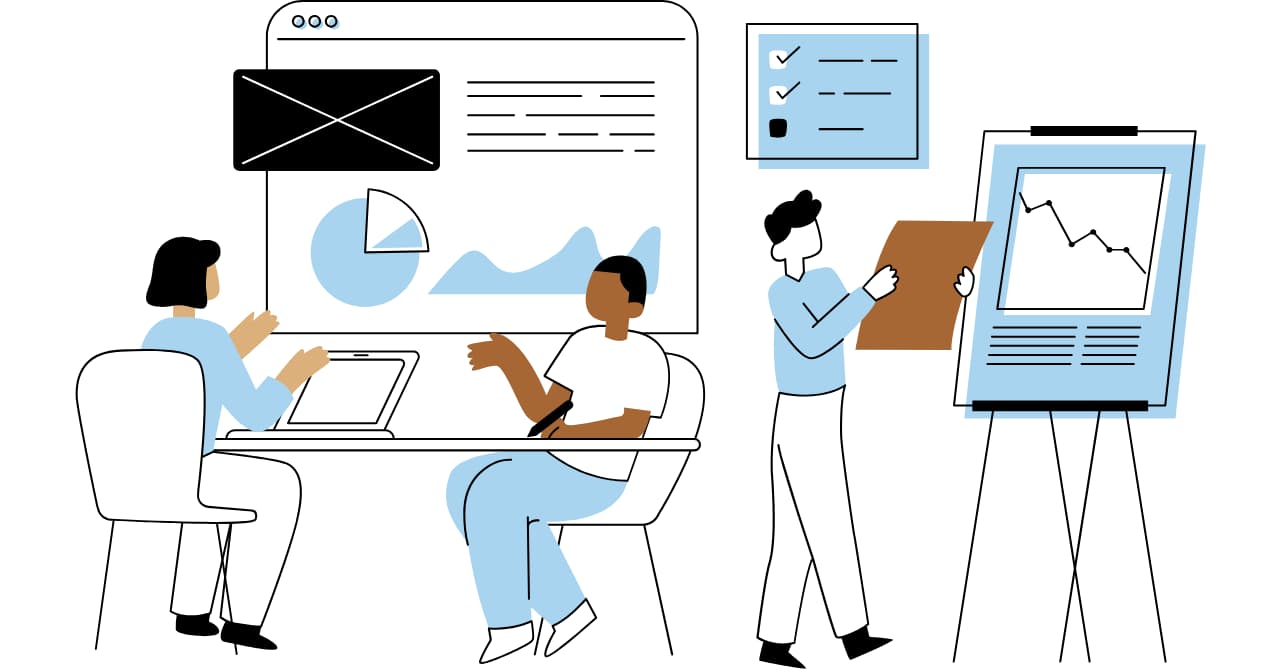
空売りにはさまざまな場面で活用できる方法があります。
ここでは、実際によくある3つの例をご紹介いたします。
1. 業績が悪くなると予想した場合
例えば、XYZ株式会社という企業が、もうすぐ決算発表を行うとします。
最近のニュースなどから、XYZは売上が落ちていて、さらに原材料の値上がりやライバル企業との競争が激しくなっているという話が出ていたとしましょう。
このような状況では、「決算はきっと悪いのではないか」と予想する投資家が出てきます。
そこでXYZの株を空売りしておき、決算の内容が本当に悪かった場合、株価は下がる可能性が高くなります。
株価が下がったあとに安い値段で買い戻せば、その差額が利益となります。
2. 業界全体の流れから判断する
ある業界全体が不調に向かっていると感じたときも、空売りが使えることがあります。
例えば、電気で動く車の業界(電気自動車業界)で、新しい技術の遅れや、国の決まりごとの変化などによって、将来が少し不安になっているとします。
このような時期には、業界の中でも有名な企業(たとえば、ABC自動車株式会社)の株も、全体の流れに押されて値下がりすることがあります。
そこで、そのような企業の株を空売りしておけば、業界全体が落ちこみ、株価が下がったときに買い戻すことで利益を得ることができます。
3. 株価が上がりすぎていると感じたとき
株式市場が全体的に盛り上がっているとき、一部の銘柄が「さすがに上がりすぎでは?」と思えるような株価になることがあります。
例えば、DEFテクノロジー株式会社という企業の株価が、業績やこれまでの成長スピードに比べて、明らかに高すぎると感じたとしましょう。
このような「熱くなりすぎた相場」は、ある日突然、冷めてしまうことがあります。いわゆる「バブルがはじける」ような状態です。
そこで、DEFテクノロジーの株を空売りしておき、株価が元の水準に戻ったときに買い戻すことで、差額が利益となります。
空売りのよくある質問

Q1. どのようなタイミングで行うと良い?
空売りを始めるタイミングは、株価が下がりそうな時が基本です。
たとえば、その会社の業績が悪くなったときや、世の中のニュースが株にとってマイナスになる場合などです。
また、チャートを使った分析では、「移動平均線」が下向きに交差するタイミング(デッドクロス)や、過去の高値で反転したときなどがよく使われます。
株価が上がりすぎたあとに、一度下がることも多いため、そのような場面も狙い目の一つです。
Q2. どれくらいのお金(証拠金)が必要?
空売りには「証拠金」という、予め預けるお金が必要です。
この金額は、株を買う場合とは少し仕組みが違い、たいていは取引額の30〜40%ほどになります(証券会社によって差があります)。
もし相場が思わぬ方向に動いて損が増えると、「追証」といって、さらにお金を入れないといけなくなる場合もあるので、無理のない範囲で取引することが大切です。
Q3. 使える指標やチャートの見方はある?
はい、いくつかのチャートの見方や数字を参考にすることで、空売りのタイミングを見つけやすくなります。
例えば、移動平均線のデッドクロスや、ボリンジャーバンドの上限に近づいた時、RSIやMACDが売られ過ぎを示唆している時がエントリーポイントになります。
こういった場面は、株価が反転して下がりやすいと言われています。
さらに、その会社の決算内容や業績など(=ファンダメンタル)もあわせて見ることで、より確かな判断がしやすくなります。
Q4. 配当金や株主優待はもらえる?
空売りをしているときは、配当金や株主優待を受け取ることはできません。
むしろ、配当がある会社の場合、「配当落ち日」になると、その分の配当金を相手に支払わないといけないこともあります。
このような追加の費用が発生する点には、事前に気をつけておく必要があります。
Q5. リスクを減らす方法はある?
空売りのリスクをおさえるには、いくつかの方法があります。
たとえば、同じ業種の中で強い銘柄を買っておくことで、全体のバランスをとる方法があります。これにより、空売りで損が出たときに、もう一方でその損を補うことができます。
また、少しむずかしい方法としては、「プットオプション」という仕組みを使うことで、空売りの損を防ぐこともできますが、初心者の方にはあまりおすすめできません。
まずは、無理のない資金で小さく始めて、ルールを守りながら経験を積むことが大切です。
まとめ
空売りは、株価が下がることで利益を出す方法です。上がる時だけでなく、下がる時にもチャンスがあるのは大きな強みと言えます。
一方で、株価が思ったよりも上がってしまった場合、損がどこまでも大きくなってしまうおそれがあります。
さらに、貸株料や逆日歩といった、ふつうの売買では発生しない費用もあるため、事前にしっかり確認することが必要です。
空売りを成功させるには、チャートの動きや会社の情報をしっかり調べ、感情にまかせずに冷静な判断を行うことが欠かせません。
焦らず、コツコツと知識と経験を積みながら取り組んでいきましょう。