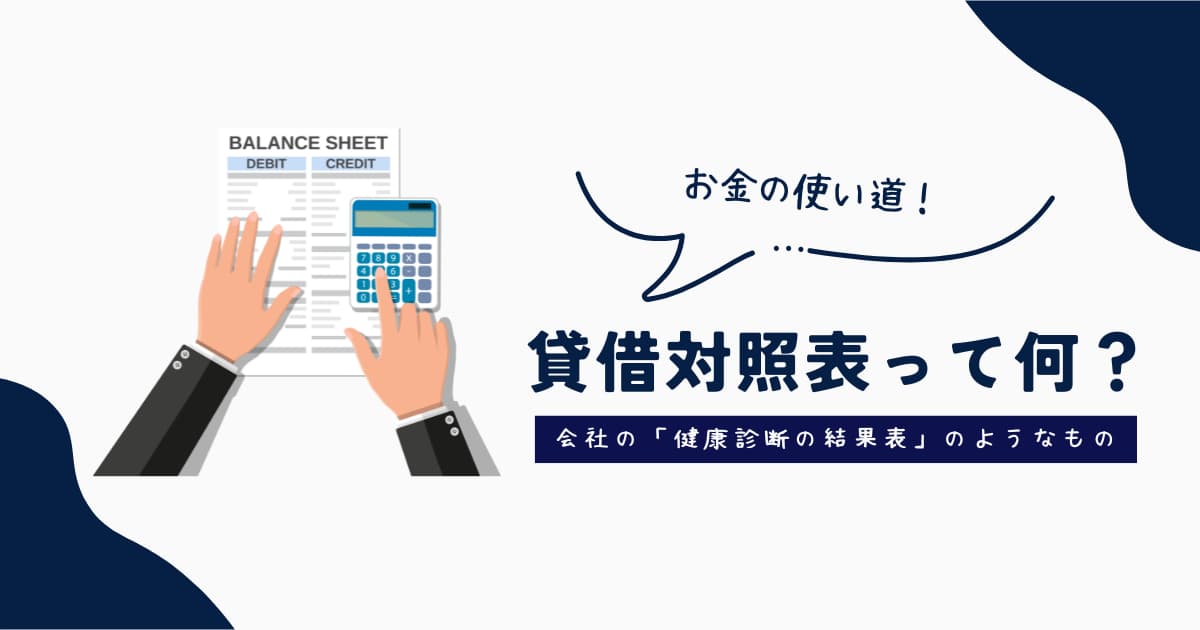「貸借対照表って、むずかしそう…」そう感じたことはありませんか?
ですが実は、ポイントさえつかめば、会社のお金の流れがひと目でわかる便利な表なんです。
この記事では、誰でも分かるように「貸借対照表(バランスシート)」の見方を解説します。
なぜ大切なのか、どう役立つのかをやさしくお伝えしますので、会計の知識がない方でもご安心ください。読めるようになれば、会社の元気さや危なさまで見抜けるようになりますよ。
貸借対照表は単体でも重要ですが、損益計算書やキャッシュフロー計算書とあわせて読むことで、企業の状態をより正確に把握できます。
貸借対照表(バランスシート)って何?

貸借対照表は、会社の「お金の使い道」と「集めたお金の出どころ」を表にしたものです。
これを見ることで、会社がどんなふうにお金を使っているのか、どれくらいの借金があるのか、どのくらいお金やモノを持っているのかがわかります。
言いかえると、会社の「健康診断の結果表」のようなものなんです。
貸借対照表は、次の3つで成り立っています。
- 資産:会社が持っているモノやお金
- 負債:会社が借りているお金
- 純資産:かんたんに言えば、自分のお金(資産−負債)
たとえば、お店でいうと…
- レジにある現金 → 資産
- 銀行から借りたお金 → 負債
- お店を自分のお金で建てた分 → 純資産
となります。つまり、どこからお金を集めて、何に使っているかが全部わかるんですね。
貸借対照表は、「今の会社の体力」がわかるとても大事な表です。
お金の流れが一目でわかるので、投資をする人や経営をしている人にとって欠かせない道具のひとつです。
貸借対照表(バランスシート)はどこで見られるの?

貸借対照表は「決算短信」や「有価証券報告書」に掲載されています。
決算短信の読み方については、決算短信とは?株初心者が知っておくべきポイントで詳しく解説しています。
では、どうやって見るのかというと、以下のような方法があります。
- 企業の公式ホームページにある「IR情報(投資家向け情報)」
- Yahoo!ファイナンスの「適時開示」
- 株探サイトの「開示情報」ページ
- マネックス証券など証券会社のサイト
中でも特におすすめなのが【株探】です。
なぜなら、貸借対照表だけでなく、過去の業績や利益の変化、会社の成長の流れなども一目で分かるからです。
貸借対照表(バランスシート)の構成

企業のお金の状態をあらわす「貸借対照表」は、大きく分けて3つの部分からできています。
それは「資産」「負債」「資本(純資産)」です。
これから、その3つについて順番にご説明します。
1. 資産ってなに?
企業が所有する全ての資産
資産とは、会社が「持っているもの全部」です。将来お金に変えられるものをさします。
資産は、会社の強さをあらわします。たくさん持っていれば、それだけ会社は安心できますし、何かあっても対応できます。
資産には、いろいろな種類があります。
- 現金や預金
- 商品や材料(お店で売るモノ)
- 建物や土地
- 人に貸しているお金(売掛金など)
- 工場で使う機械や道具
たとえば、おにぎり屋さんなら…
- おにぎりをつくる米や海苔 → 商品
- お店そのものやキッチン → 建物・道具
- お客さんからの売上がまだ未払いの分 → 売掛金
これらぜんぶが「資産」となります。
資産は、会社が持っている「お金やモノのチカラ」です。

2. 負債ってなに?
企業が返済義務を負っている全ての借入金や債務
負債とは、かんたんに言うと「会社が返さないといけないお金」です。
どれだけ借金があるかを知ることは、会社の安全度をはかるうえでとても大切です。
負債には、次のようなものがあります。
- 銀行などからの借入金(ローン)
- お客さんや取引先にまだ払っていないお金(買掛金)
- 給料の未払い分
- 税金の未払い分
たとえば、ケーキ屋さんがオーブンをローンで買った場合、そのローンが「負債」です。また、材料費を後払いにしているなら、その支払いも負債に含まれます。
負債が多すぎると、返せなくなるリスクがあります。

3. 資本(純資産)ってなに?
資産から負債を差し引いた残りの部分
資本(純資産)は、会社が本当に持っている自分のお金です。資産から負債を引いた残りが純資産です。
純資産を見ることで、会社がどれくらい「借金に頼らず運営できているか」がわかります。
たとえば、こんなイメージです。
- 資産が1,000万円
- 負債が600万円
この場合、純資産は「1,000万円 − 600万円 = 400万円」になります。つまり、400万円分は自分のお金で動かしているということですね。
純資産にはこんな種類があります。
- 資本金(会社を作ったときの元手)
- 利益の積み重ね(内部留保)
純資産が大きければ大きいほど、会社は「自力でしっかりやってきた」ことを意味します。

純資産をより深く理解するには、自己資本比率やBPS(一株当たり純資産)といった指標もあわせて確認すると効果的です。
貸借対照表(バランスシート)の見方と分析の仕方

貸借対照表を正しく読みとることで、その会社のお金の状態や、これからの成長の力が分かります。ここでは、大切な分析のポイントと、注目すべき数字について説明いたします。
1. 財務が健全かどうかをチェックする方法
企業の財務状態が良いかどうかを知るには、「短い期間での支払いにきちんと対応できるか」「大きな資産を無理なく持っているか」といった点に注目することが大切です。
以下の3つの指標がとても役立ちます。
・流動比率
まず「流動比率」は、短期間で使えるお金が、短期間で返さなければならない借金をどれだけ上回っているかを示します。
- 計算式:流動資産 ÷ 流動負債 × 100(%)
- 目安:150%以上が望ましいとされています。
たとえば、流動資産が300万円、流動負債が150万円なら、流動比率は200%となり、短期の支払いに強いと判断できます。
・当座比率
「当座比率」は、流動比率よりもさらに厳しく会社の支払い能力を測る指標です。在庫はすぐにお金にならないことがあるため、これを除いた「より確実に使えるお金」で評価します。
- 計算式:(流動資産 − 在庫)÷ 流動負債 × 100(%)
- 目安:100%以上が安心の基準とされています。
この比率が高ければ高いほど、今すぐの支払いにしっかり対応できる体力のある会社だといえます。
・固定比率
「固定比率」は、会社が持つ工場や設備といった長く使う資産を、自分のお金(自己資本)でどれくらい賄っているかを見るものです。
- 計算式:固定資産 ÷ 自己資本 × 100(%)
- 目安:100%未満が理想とされます。
この比率が低いと、自社の資金で設備を整えており、借金に頼らない健全な経営ができていると判断できます。
2. 資資産の質を見きわめる
企業がたくさん資産を持っていても、その中身がすぐにお金になるものなのか、利益を生み出しているのかが重要です。ここでは「資産の中身」に注目していきましょう。
・流動性
流動性とは、どれくらい早くその資産が現金に変えられるかを示す性質です。流動性の高い資産が多ければ、急な支払いにも柔軟に対応できます。
たとえば、下の表をご覧ください。
| 資産の種類 | 流動性の高さ |
| 現金・預金 | とても高い |
| 売掛金 | 高い |
| 在庫 | やや低い |
| 土地・建物 | 低い |
投資を考えるうえでも、流動性の高い資産がどれだけあるかを確認することは重要です。
・収益性
もう一つ大切なのは、資産がしっかり「働いているか」です。会社が持つ機械や土地、建物などが、しっかり利益を生んでいるかを確認しましょう。
設備が動いていて生産に使われていれば、もうけに貢献している。逆に、使われていない設備や空き地ばかりでは、資産が眠っていることになる
つまり、数字だけでなく、その資産が実際に役立っているのかどうかを見極めることが大切なのです。
3. 借金の内容をチェックする
・負債比率
負債比率は、会社全体の資産のうち、どれくらいが借金でできているかを示します。
- 計算式:負債 ÷ 総資産 × 100(%)
- ポイント:高すぎると借金への依存が大きく、経営が不安定になる可能性があります。
とはいえ、業種によっても適正な水準は異なるため、同じ業種の他社と比べることが大切です。
・自己資本比率
自己資本比率は、会社全体の資産のうち、自分のお金(自己資本)がどのくらいを占めているかを示す指標です。
- 計算式:自己資本 ÷ 総資産 × 100(%)
- 一般的な目安:40%以上あれば、安定した会社と考えられることが多いです。
この比率が高いと、借金に頼らず、しっかりとした土台のある企業と判断できます。
4. 自己資本の増え方と成長の力をみる
最後に注目すべきなのは、「これまでの儲け」がどれだけ会社の中に残っていて、それが将来の成長につながっているかです。
過去の実績とこれからの期待の両方を見ることで、企業の可能性が見えてきます。
・剰余金(内部留保)
剰余金とは、会社が過去に得た利益のうち、配当せずに社内に残したお金のことです。このお金は、新しい工場を作ったり、研究開発に使ったりと、会社の成長のために役立ちます。
剰余金が年々増えている会社は、しっかり利益を出し、その利益を会社に蓄えている証拠といえます。
・利益剰余金率
この指標は、剰余金が自己資本全体の中でどれくらいの割合を占めているかを表します。
計算式:利益剰余金 ÷ 自己資本 × 100(%)
高ければ高いほど、過去の利益が会社の基盤となっていると判断できます。
このように、貸借対照表は「会社の成績表」のようなもので、将来性を見抜くためのヒントがたくさん詰まっています。
数字をただ見るのではなく、「この会社は今、どんな状態なのか?」「これから伸びていける力があるのか?」という視点を持って読むことが重要です。
貸借対照表(バランスシート)のよくある質問

Q1. どのくらいの頻度で作られるの?
多くの会社では、3か月に1回または1年に1回のペースで作られます。これは、会社の経営状況を定期的に見直すためです。
大きな会社は、毎年や四半期ごとに発表しますが、一部の会社では毎月つくることもあります。会社によって頻度は違いますが、少なくとも年に1回は作成されます。
Q2. なぜ「バランスシート」とも呼ばれるの?
貸借対照表は、数字が左右でバランスがとれていることから「バランスシート」と呼ばれます。「資産=負債+資本」というルールに基づいて作られているからです。
たとえば、100万円の資産がある場合、そのお金の元が「借りたお金(負債)」と「自分のお金(資本)」で100万円になるよう計算されています。
このように、どこから資金を集めて何に使っているかを左右で表すことで、全体が均等になる仕組みです。
Q3. 負債が多いとどうなるの?
借金が多いと、将来の支払いが増えるため、会社にとってリスクが高まります。利息を払う必要があり、返済ができなくなると経営に悪い影響が出ることもあります。
無理にお金を借りて事業を広げた結果、利益が出ずに返済に苦しむ会社もあります。ただし、計画的に借りれば成長のチャンスにもなります。
負債は多すぎると危険ですが、上手に使えば会社を大きくする力にもなります。
Q4. 貸借対照表だけで成長性は分かる?
この表だけでは、会社が今後伸びるかどうかを判断するのは難しいです。 貸借対照表は「今の状態」を表しているため、これからの成長を知るには別の資料も必要です。
利益の動きを見る損益計算書や、お金の出入りを見るキャッシュフロー計算書などもチェックしましょう。貸借対照表は大切ですが、他の資料とあわせて読むことがポイントです。
株価水準まで判断したい場合は、PBR(株価純資産倍率)も参考になります。
Q5. どうやって分析すればいいの?
いくつかの数字を使って会社の力をチェックするのが基本です。
数字を比べることで、会社がどれくらい元気か、借金を返せる力があるかが分かります。
具体例: 「流動比率」「負債比率」「自己資本比率」などを使って、会社の支払い能力や安定性を調べるのが一般的です。
難しそうに見えますが、見るポイントを絞れば、初心者でも理解できます。
Q6. 分析するときに気をつけることは?
1つの会社だけを見るのではなく、他の会社や過去と比べることが大切です。
数字の意味は、比べてみないと本当のところが分かりません。
たとえば、自己資本比率が30%でも、同じ業界の会社が平均50%なら注意が必要です。また、過去の数値とくらべて良くなっているかどうかも確認しましょう。
数字の背景にある「経営の方針」や「市場の動き」にも目を向けましょう。
まとめ
貸借対照表は、会社の「お金の鏡」ともいえる大切な表です。なぜなら、会社にどれだけの財産があり、どれくらい借金があるのかをひと目で知ることができるからです。
見方を覚えてしまえば、会社の強さや弱さを自分で判断できるようになります。
難しそうに見えても、今回の内容を思い出せば大丈夫です。少しずつ慣れていけば、だれでも読めるようになります。